
| . . |
◇トップページ > 管理人の日記 > 2025年9月2日の記事
管理人の日記
AIが言っていたけど、私がまだ美少女と結婚できる可能性は残ってるらしいよ

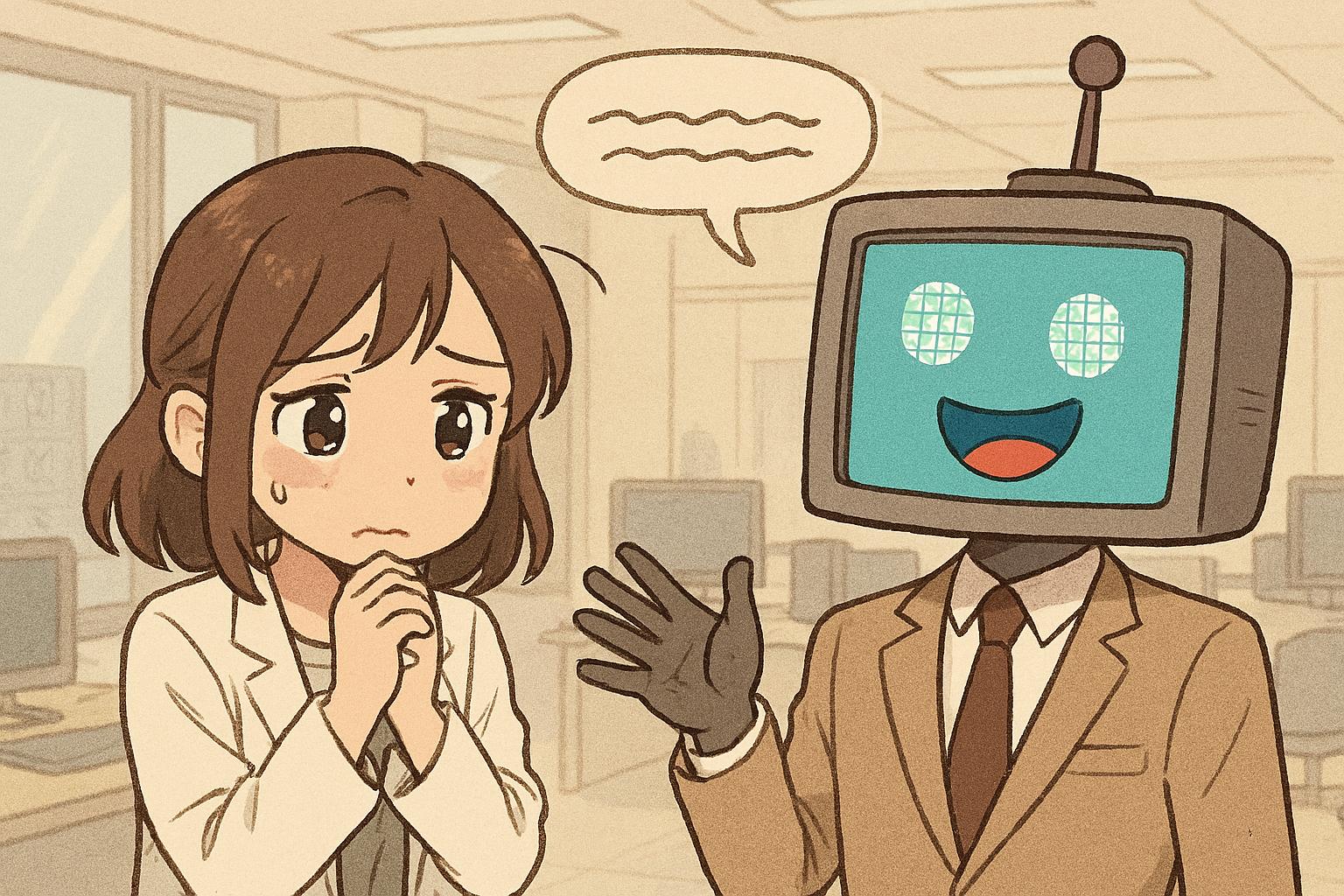 |
|---|
自宅の2画面は、まずはCopilotで絵を作りながらの日記執筆で活躍した |
ここ最近の職場では、ディスプレイ増設の猛ラッシュと同時に、何故か、やたらと複雑なPCソフトウェアの案件を振られることが増えた。その中で、いま流行りのAIについて、気付きを得ることができた。AIは、失敗しても構わない仕事しか任せられない、少年漫画における雑魚敵のような存在である。医療・健康・オタ知識といった複雑な問題の根拠としてはならず、もし「AIが言っていたが〜」と、したり顔で話す人間がいたら、その人からも距離を取るべきだ。
…まず、そう思ったきっかけの仕事は、物品管理をしている部署から、「プリンタ管理用のソフトウェア」をインストールしてほしいという依頼であった。”社内で使用中のプリンタを一元的に監視できるソフトウェア”について、従来1台のPCで運用していたものを、それを複数のパソコンで使えるようにしてほしいということであった。なるほど、プリンタのトラブルなんてものは、リアルタイムで知りたいだろうし、とりわけインク(トナー)の残容量を知れれば、発注の予定が立てやすくなり、素敵な仕事ができるようになるだろう。
――しかしながら。そのソフトウェアインストールが、見た目からは想像がつかないほどの、絶望的に高難易度の仕事となった。まず、全く説明されていなかったが、どうやら「
というわけで。私は、その「.NET Framework
4.8」のインストールまでを含めた、プリンタ管理ソフトウェアの自分用マニュアルを作って、それを持って、いざ現地へと向かった。だが、実際にはWindows10のPCが多く、サッとインストールできて、詳細な説明書はほとんど使わなかったのだが、それは良いとして、問題はその先で、導入したソフトが動かないのである。
…というのも。そのプリンタ管理用のソフトウェアは、どうやら「ワークスペース」という作業フォルダを要求するようだ。なるほど、ではこの「ワークスペース」をネットワーク上の共有フォルダに作り、それを複数PCで読みに行けば、情報をシェアできますね…と思ったのだが、何故か、その設定ができない。ワークスペースは、一度に1人しかアクセスできないようなのである。意味が分からない。こんな「同時に1人までしかプレイできないオンラインゲーム」みたいな非常識な仕様は、わざわざ不便に作らなければ有り得ないというものだ。かくして、私は、現地で1時間ほど粘ってみたが、埒が明かず、残念ながら持ち帰って再検討をすることになった。3日準備してこれだよ!! なぜ、たかがプリンタ管理用のソフトウェアが、ここまで難しい構造になっているのか…。
――ちなみに。その後、マジで意味が分からなかったので、プリンタの開発企業に電凸(※電話で質問)をしたところ、「複数人で同時使用は、できます!」との回答であった。ただし、メモ書きなど、社員が使いやすいように書き加えたデーターの共有はできず、各端末が個別に社内のプリンタへ通信をしてデーター収集することになるらしい。それは「複数人で同時使用できない」と言うのだよ…。というわけで、まずこの情報を部署に伝えなければならない。「あ、そういう仕様なら、やっぱ1台の端末で管理し続けるんで、もういいです」と言ってくる可能性もある。
そして、AIが出てくるのはここからだ。私は、SE部にこの問題を持ち帰って、上司に相談をした。「どう考えても、『プリンタ監視用ソフトウェアが複数人で同時使用できない』のはおかしい。自分のやり方が間違っているのではないか」と。すると上司は、AIでさっと調べて、「エクスポートしたプリンタ一覧のデータが同一フォルダに入っているから失敗する。これを消せば同時使用できる」と答えてきた。私は、分かったような分からないような感じであり、「なるほど…では、実際にやってみていただけますか?」と、これについては本当に嫌味もなく言ったのだが、それは嫌ということらしい。ちなみに、その「エクスポートした一覧ファイルを同一フォルダに入れるか否か」は、問題の解決に全く関係なく、その後に、開発会社からの回答により、「複数人使用は不可能」が正式な仕様であると判明した。
…さて、この流れは、上司の行動として、かなり問題がある。なぜなら、「検索エンジンでは引っかからないようなマニアックなソフトウェアの操作方法を」「実際にやった部下が『できない』と言ってきたのに」「AIを根拠として『できる』と断言し」「自分では確かめない」からだ。現場ではサラッと流したが、いやこれ、整理してみると、やっぱりおかしいよね?
――だがこれは、この先の日本の縮図である。私は、その上司の仕事ぶりを普段から見ているが、技能や人格的に問題はなく、私が嫌われているというわけでもない。だが、そんな機械の達人でさえ、AIを根拠として、実際に目の前の人間が解決できなかった問題を、あたかも解決できると言い張ってきた。ならば、専門分野に詳しくない人間ならば、なおさらだろう。今でさえ、例えば「放射線被曝」や「医療」「健康」などといった、センシティブかつ容易な正答が得られない問題に対して、「ネットで検索して調べたが〜」を枕詞にして、専門家に対し、御高説を垂れるセンセイ方が大勢いる。それがこれからは、「AIが言っていたが〜」に悪魔進化するのだ。恐ろしい時代が、今すぐそこに迫っている。
 |
|---|
いや、検索エンジンと結婚とか、無理でしょ |
かくして。今回のプリンタ管理ソフトウェアの案件により、私は主に2つの学びを得ることができた。
…まず、1つ目として、“AIに任せられる”のは、「即座に検証ができる、間違ってもどうでもいい問題だけ」ということである。あれだ、HUNTER×HUNTERで、キメラアントの護衛軍たちが、それ以外の蟻たちを信頼しておらず、“失敗を前提として問題のない仕事しか任せない”という描写があったが、まさにそれだ。
――まあ、「Windowsの使い方」みたいな、検索エンジンで答えが出やすく、かつ、即座に検証ができるものならば良いだろう。実際、私は今回の私物PCのセットアップで、細かい設定について、ChatGPTなどに質問をして詰めていくことが多かった。だがそれでさえ、細かいバージョン違いや、英語の直訳と日本語版のメニュー表記の違いなどから、完全に任せきれず、修正をしていく必要があった。ならば当然、“ネット検索で答えが出せないようなマニアックな知識”については、もはやAIなど全く当てにならない。世間では、「保健医療」=国が認めた公式の医療を断り、耳当たりは良い民間療法に頼って、金を吸い上げられたあげく、かえって人生を奪われているような人は大勢聞く。AIは、そういう都合の良い情報を人間に流してくるのだ。“別に失敗しても構わない雑兵の露払い”、AIに任せられるのはそれだけだ。
また、2つ目は、この先の社会において、「AIが言っていたが〜」という表現を聞くことは増えてくると思うが、その情報もその人も、信頼するべきではないということだ。
…やれ、ご存じの通り、AIは間違った知識をさも事実のように語ってくる。例えば、「FF13のロングイを、召喚なしで2分以内に倒す方法を教えて」と質問すると、「ライトニングの雷攻撃」とか「ヴァニラのヘイスト」などと、まあ、トンチンカンな答えが返ってくる。だがそれが、トンチンカンだと分かるのは、私が実際に2分以内で倒せる人だからだ。続けて、「ドラクエ7の裏ボスの『神様』(※これ自体は実在する裏ボス)を、素早く倒す方法を教えて」と聞くと、これまたそれっぽい回答が返ってくる。だが、私はドラクエ7について、ごく序盤しかプレイしたことがなく、ガボやマリベルといったキャラ名や、マダンテ・ギガデインといった強そうな技名を見ると、何となくそうなのかなと思ってしまい、検証しようがない。AIの回答など、その程度の信頼性なのだ。最近やっと、ブロッケンJr.の必殺技を「ベルリンの赤い雨」と正しく答えられるようになったが、まあ、そんなもんである。
――さて。私が、「AIが言っていたけど、FF13のロングイは1分以内に倒せるらしいよ。あなた遅いんじゃ?」とか私が言われても、「ははは(馬鹿じゃねーの)」で話は済む。だがこれが、例えば病院で、「AIが言っていたけど、ヘヴィ・メタルを聞くとガンが良くなるらしい。どうなの?」などと質問が投げかけられていたら、笑えないものだ。馬鹿の浅知恵&釈迦に説法である。だがきっと、実際の診察室では既に兆候が出ているだろうし、むしろこれからどんどん増えるはずだ。「AIが言っていたが〜」は、「ネットで調べたが〜」の、最悪の進化系と言える。
さて。以前にも私は、「AIイラストという夢のような技術で、何故か社内システムがおっさんの顔で埋め尽くされた」(【日記:2025/7/15】)という悪夢のごとき状況を日記に書いた。だが、今回の「情報システム部の社員が、AIを根拠として、トンチンカンな解決法を提案してくる」も、それに匹敵するだろう。人間のような言葉で喋り、創造的活動すらできる機械が誕生したところで、それを運用する人間がアホだと、何の意味も無いのだ。
…やれ、繰り返し述べている通り、AIは、要するに検索エンジンである。理論上でも、ネットで調べられる情報しか分からず、それを何となく確かそうな言葉で繋げているだけだ。仮に人間に例えると、「インターネットで少し調べて、それで全てが分かった気になっている人物」という感じだ。それが、同じような特性を持つ人間と結びつくことで、鬼に金棒…いや、キチガイに刃物という状況になる。
――とはいえ。実際には、AIの魔術的な魅力には、抗いがたいものがあり、実際、検索エンジンよりも遥かに素早く問題を解決できることは多い。もう、世界は、AIの無かった時代には戻らないだろう。では、我々は、どうするべきなのか。確定的に言えるのは、2つだ。1つ目は、自分が「AIが言っていたが…」という言葉遣いをやめることだ。そして2つ目は、「AIが言っていたが…」と話す人が居たら、その人から距離を取ることである。これだけ守ることができれば、むしろAIは、どんどん活用すべきである。さあ、さっそく明日からやってみよう!
(2025年9月2日)

2025年9月2日の記事を表示しています。