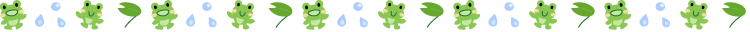
| . . |
◇トップページ > 管理人の日記 > 2025年5月3日の記事
管理人の日記
あ、戦争放棄とか夫婦別姓とか概念的な話は後でいいんで、コメと油と給料にかかる税金さげてください
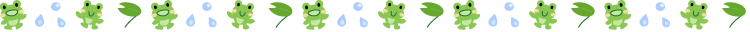
 |
|---|
この3人が出てきたくらいの頃は、まだ楽しめていたが… |
少し前から、アニメ版の「BLEACH」を見ており、第2シリーズと言える「
…さて、「バウント篇」は、アニメオリジナル=原作漫画に無いエピソードであり、「尸魂界篇」と、仮面の軍勢?
なる敵が出現するという「破面篇」の間に挟まっている。全46話という長さは、「尸魂界篇」とほぼ同じであり、アニオリとしては最長であるそうだ。実放送期間としても、丸1年と長大であり、2006年1月から2007年1月まで放送されたということらしい。
ちなみに。一般的な話として、レギュラー放送されていた頃のジャンプアニメにおいて、“アニメオリジナルエピソード”というのは、あまり評判が良くないことが多いらしい。しかしながら、私は特に抵抗感を持っていない。何故なら、アニメ「遊戯王」のアニオリが好きだったからである。
…やれ、シリーズ第1作「デュエルモンスターズ」(全224話)では、原作漫画をベースとしつつも、遊戯王カードの宣伝アニメという性質と、そして既にテレ朝版(「無印」「初代」「東映版」などとも)が存在していたという都合上、“第1話で物語のダイジェストをして、第2話から王国編を始める”という放送形式になった。途中、概ね原作通りに進めつつ、細かいオリジナルデュエルなども入れられていたが、それだけでは原作に追いついてしまうためか、途中で、長めのアニメオリジナルエピソードが、何度か挿入されることになった。
――その中で、主要な物は、“バトルシティ編:決勝トーナメント”の1回戦から2回戦の間に挿入された「乃亜編」(全24話)、そしてバトルシティ終了から王の記憶編までの間に放送された「ドーマ編」(全40話)、それに続く「KCグランプリ編」(全14話)の3つであると言える。
さて、これらについては、とりわけ「ドーマ編」については、当時のOCG環境から見るとぶっ壊れたカードたちと、原作のキャラクター性と異なるような描写も見られることから、「否」寄りの賛否両論と捉えられているようだ。
…ただ、私は、このドーマ編が、それこそ、初代アニメで一番好きと言えるくらいに気に入っている。理由として、ストーリーの壮大さや、作画・BGMの良さ、登場キャラ&カードの個性などもあるが、最も大きい理由は、「アニメオリジナルであること」だ。私は、原作漫画の遊戯王を読んでおり、アニメ版についても、“漫画版の映像化”という気持ちで視聴していた。そして、バトルシティ編が終わり、石板に神のカードをかざしたところで、ここから最終章が始まるんだなーと、思っていたところ、いきなり、アニメオリジナルのルートに分岐した。そして、遊戯・城之内・海馬といった主要キャラたちが、未知の敵と戦い始めた。見知ったはずの遊戯王で、まったく新しい展開がスタートしたのである。この気持ち、例えるならば、名作ゲームに追加要素が現れたとでも言おうか。各種の衝撃的な展開も、むしろ「アニメオリジナルで、よくそこまで攻めてくれた!」という感じである。
――やれ、私は、遊戯王デュエルモンスターズを、幾度となく1話から再視聴をしている。しかし、その中でも、「ドーマ編」は、最も楽しみと言えるエピソードだ。もちろん、「乃亜編」「KCグランプリ編」も好きであり、これらのアニメオリジナルも含めたうえで、初代遊戯王という感じだ。
そんなわけで。私は、「BLEACHのアニメオリジナルは、あまり面白くない」と聞いていたものの、全く不安を感じていなかった。むしろ、「遊戯王のアニオリと同じく、世間で批判されていたとしても、自分には楽しめる」と自信満々であった。そもそも私は、BLEACHの漫画原作をごく序盤しか読んでおらず、「原作エピソード」と「アニメオリジナル」を、特別に区別していない。そのため、面白ければ何の問題も無かったのだ。
――かくして。大満足で「尸魂界篇」を見終えたあと、それに続く「バウント篇」も、最初は目を輝かせて見ていたのだ…。
 |
|---|
私「何なんだこのシーン…」 |
では、「バウント篇」の何がそんなにつまらないのか。私が感じたのは、皆が言っていることだが、長すぎるという点だ。
…やれ、バウント篇は、前述の通り、46コ話という、実時間で1年に渡る長編エピソードだ。ほぼ同じ長さの「尸魂界篇」は、恐らくだが、BLEACHの方向性を決定づけたと言えるくらいの、名エピソードである。では、それと同じだけの内容や魅力が「バウント篇」にあるかというと、全く無い。
具体的には、序盤に、“3体の改造魂魄”たちが現れて、剣術ではない、様々な形式のバトルを挑んでくるところは、まだ良かった。キャラデザも個性的で、戦闘についてもこの時点では新鮮であった。前シリーズの興奮がまだ残っていたということもあったかもしれない。
…しかし、ひと段落が付いた後に登場する、メインと言える敵:「バウント」たちは、もうダメダメである。吸血鬼モチーフであり、「ドール」という召喚獣のような特殊能力を持っていることなどから、あえて原作の雰囲気に寄せず、キャラデザも、それまでと変えていくことにしたのだろう。しかしながら、どう考えても、モブにしか見えないのだ。
――やれ、アニメというのは、映像の娯楽であるのだから、見た目が最も重要というのは、言うまでも無い。有り得ないくらいの奇抜な服装や髪型で、「なんかまた変な奴が出てきた…」と視聴者に脅威を与えるくらいのほうが、むしろ最終的には親しめる。少なくとも、私は、“BLEACHのキャラデザの魅力”は、そういうところにあると思っている。
加えて。このシリーズ自体が、最初から1年の放送と決まっていたためか、バウントとの戦闘においては、戦っても決着がつかず、勝負なしになってしまうことが非常に多い。中盤、現世にてちょっとした山場があり、味方側の主要キャラたちと、敵幹部たちが激突する。だが、ほぼ勝利と言えるような状況でも、敵側が逃げ帰って引き分けになることがほとんどで、私は呆れてしまった。こんな魅力の無いキャラたちを引き伸ばすのか? しかも、アニメ1話区切りとしても、原作に縛られていないにも関わらず内容が薄く、チンタラと進んでいく。この辺りから、私は1.5倍速を解禁したのだが、それでちょうど良いテンポに思えるくらいの、異様な遅さである。
…また、既存キャラの掘り下げになっているかというと、それもどうだか…という感じである。序盤から中盤にかけては、主要人物の一人である「石田」(※男)をヒロインばりに奪い合う展開が始まるが、その際、敵陣営の女幹部と石田が、母子のような恋愛のような、奇妙な関係に陥る。と書くと、なかなかロマンスな感じだが、見た目が普通のおばさんなので、男子高校生に好意を持つおばさん(実年齢は数百歳)という妖しい展開になり、「私は何を見せられているのだろう…」という気分に陥ってしまった。
――その後、死神界も大きくクローズアップされ、“護廷十三隊”に所属する、前シリーズの人気キャラたちが大量投入されたのは、ひょっとしたらテコ入れだったのかもしれない。ただまあ、敵に魅力が無いと、味方側の株も上がらないという感じであり、むしろ、末期のソシャゲがコラボを連発するみたいな、冷めた目で見ることになった。
やれ、これは、色々な人が色々な言い方で説明しているのだが、「長い」という感想の本質は「つまらない」である。面白ければ、それこそ50話・100話と続いても、全く悪印象を持つことは無い。逆に、バウント篇も、例えば24話や12話という単位でまとめられていれば、モブ敵の復活などもなくなって、印象もかなり変わっていただろう。しかし、実際に出てきたものが、全46話の、このバウント篇だから、それを基準に判断するしか無いのである。
 |
|---|
もはや最後の小ネタ集だけが救いだった |
というわけで。現在、BLEACHの平成シリーズについては、ちょうど100話ほどまで進んだところだ。だが、バウント篇については、中盤から、1.5倍速を解禁してしまっている。どうも、バウント篇については、残り10コ話程度ということらしい。やっと終わってくれるよ…。
――ちなみに、あえて等速再生をするところもあって、それは「次回予告」と、小ネタ集と言える「死神図鑑
ゴールデン」である。BLEACHの次回予告は、作中キャラが漫才のような掛け合いをするという、独自の形式だ。それらの、本編と関係ないおまけが最も楽しみという時点で、もう私の中で「バウント篇」がどういう扱いになっているか、ご察しいただけるであろう。
そんなわけで。「尸魂界篇」まで、非常に楽しく見ていたBLEACHアニメであったが、最近では、倍速を用いるようになっただけでなく、純粋な視聴意欲自体も低下し、そもそも食事時の娯楽として、BLEACHアニメを選ばないことも増えてきた。これは、コンテンツとして、赤寄りの黄色信号である。
…だがこれでも、まだ完結後の一気視聴というのはマシだ。もし、リアルタイムであったら、毎週毎週タラタラとした展開が続くこと、そしていつになれば終わるのか分からない不安感と苛立ちから、恐らく視聴をやめてしまっていたことだろう。
――ちなみに。バウント篇の次は、「破面篇」と呼ばれる原作エピソードである。また、この後も、平成シリーズ内で、“中長編のアニオリ”は何度か出てくるようだが、どうも原作者の監修が付いたということらしく、少なくともバウント篇ほどに不評なことは無いようだ。何はともあれ、もうバウント篇は終わるので、このまま1.5倍速で流して、次のエピソードでの巻き返しを期待することにしよう…。
(2025年5月3日)
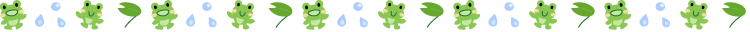
2025年5月3日の記事を表示しています。